理論が広がり始めるとき、最初に起こるのは「誤解」です。
共感翻訳も例外ではありません。この研究ノートでは、共感翻訳が「何をする理論か」ではなく、「何をしない理論か」を明確にします。
共感翻訳は、「人を変える」理論ではない
相手の考え方を修正するための理論ではありません。「分からせる」「気づかせる」「納得させる」そのいずれも、目的ではありません。
人が何をどう受け取るかは、常にその人の自由です。共感翻訳が扱うのは、人そのものではなく、人と人のあいだに生じている“意味のずれ”です。誰かを変えようとした瞬間、翻訳は介入に変わってしまいます。
共感翻訳は、「正しさを調停する」理論ではない
意見が対立しているとき、つい私たちは「どちらが正しいか」を考えますが、共感翻訳はその問いを引き受けません。「正しい/間違い」「望ましい/未熟」といったラベル付けは、翻訳を止めてしまうからです。
共感翻訳が扱うのは、どの正しさが、どの評価軸から生まれているかという構造です。正しさを揃えるのではなく、正しさが生まれた背景を並べ直す。それが共感翻訳の立ち位置です。
共感翻訳は、「共感を強要する」理論ではない
「分かってあげなければならない」という姿勢を要求しません。
- ・分かれないままでもいい
- ・納得できなくてもいい
- ・同意しなくてもいい
その前提がなければ、翻訳は成り立ちません。共感翻訳における共感とは、感情を共有することではなく、感情が生まれた構造を尊重することです。分かろうとしすぎないこと。それもまた、翻訳の一部です。
共感翻訳は、「問題解決」を目的にしない
多くの支援技法は「解決」を目指しますが、共感翻訳はそこをゴールに設定しません。関係が翻訳されることと、問題が解消されることは、必ずしも一致しないからです。
分かったが、選択は変えない。
理解したが、距離を取る。
翻訳されたからこそ、別れる。
そうした結果も、共感翻訳の射程に含まれています。「より良い結果」を約束する理論ではなく、より誤解の少ない理解を目指す理論です。
共感翻訳は、「万能な関係改善法」ではない
あらゆる関係に適用すべきではありません。力関係が極端に非対称な場面、安全が確保されていない関係、相手が翻訳を拒否している状況。こうした場面では、共感翻訳は沈黙します。
翻訳は、相互に尊重される空間があって初めて成立する行為であり、「使える場面を選ぶ理論」でもあります。
なぜ「しないこと」を先に示すのか
理論は、できることよりも、しないことが明確なときに最も強くなります。誤った期待を生まないこと、無理な適用を防ぐこと、そして使う人が疲弊しないこと。
これは理論を閉じるためではなく、必要な場面で正しく立ち上がるための準備なのです。
おわりに
何もしない勇気。踏み込まない選択。翻訳しない判断。
それらも含めて、共感翻訳という理論は成り立っています。
次の研究ノートでは、この「しない」姿勢を土台に、それでも翻訳が立ち上がる最小の一歩について扱うことになるでしょう。
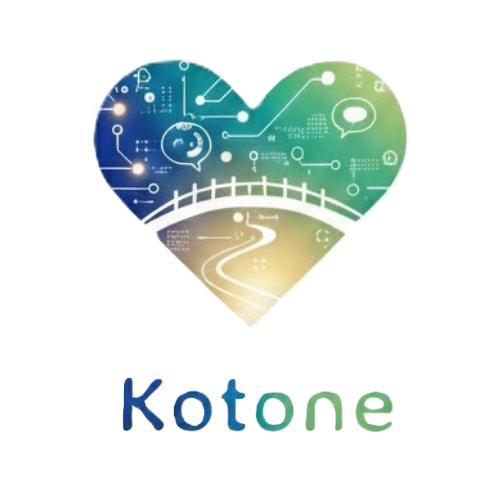
.png)







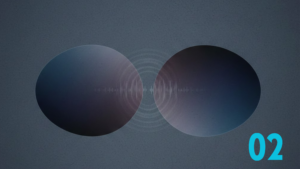
コメント